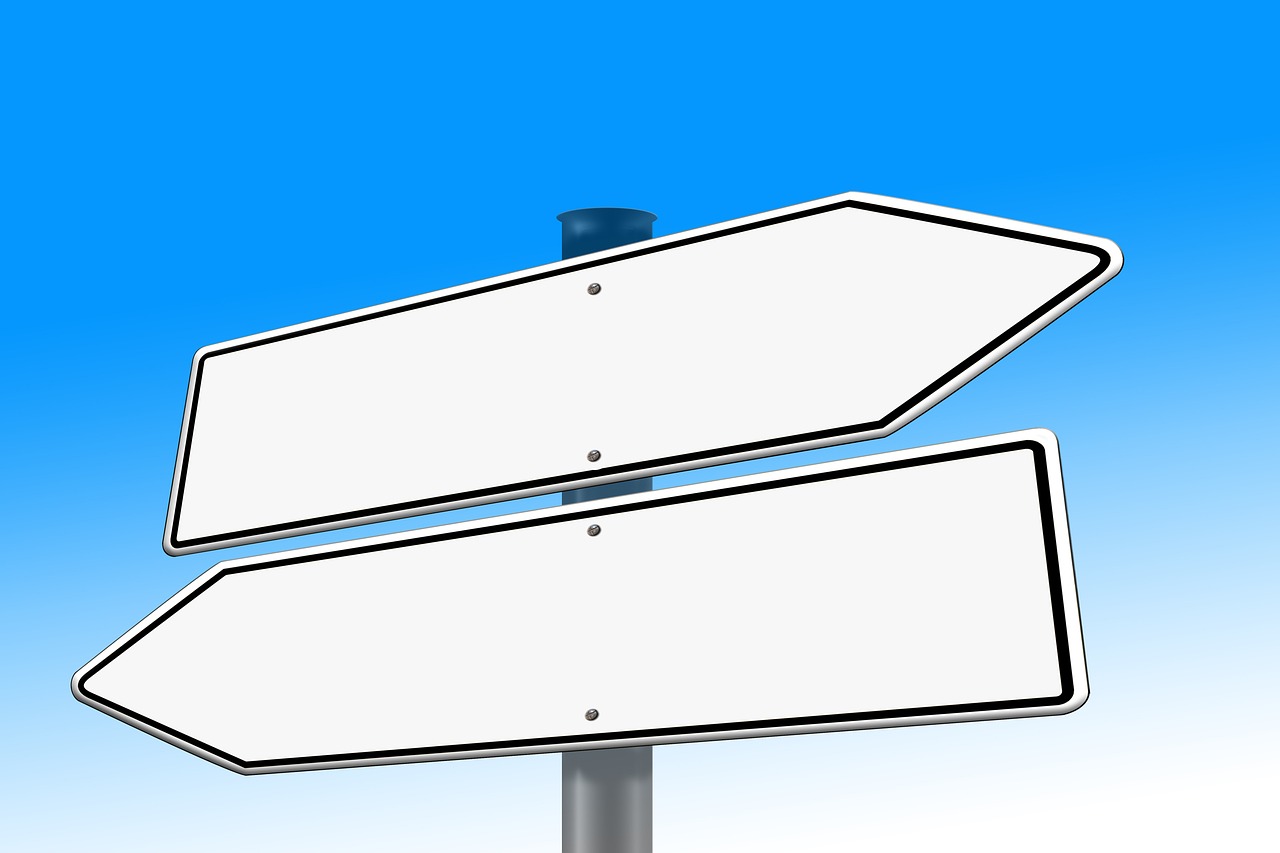東証の最低投資金額10万円引き下げ要請について

目次
はじめに
「株式投資ってお金持ちの大人だけのものじゃないの?」
そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、最近ニュースで「東証(東京証券取引所)が株式の最低投資金額を10万円程度に引き下げる方針を発表した」と話題になっています。
この記事では、なぜ最低投資金額を下げるのか、その背景やメリット・デメリット、そして若い世代にどんな影響があるのかを解説します。
「最低投資金額」って何のこと?
個人が株式投資をするには、証券会社を通して選んだ銘柄の株式を買う必要があります。
しかし通常は1株だけ買えるわけではなく、「単元株」と呼ばれるまとまった数(通常100株)で買うのが基本です。
(例)
1株500円の会社:最低投資金額=100株=5万円
1株5,000円の会社:最低投資金額=100株=50万円
つまり、「最低投資金額」とは、その会社の株を買うために必要な最低限のお金のことです。
なぜ東証は「10万円程度」に引き下げる方針を出したの?
これまで東証は「最低投資金額は50万円未満にしましょう」と企業に努力義務を課してきました。しかし、実際には50万円以上かかる会社も多く、特に有名企業ほど高額になりがちです。
そこで東証は、2024年秋に個人投資家を対象にアンケートを実施しました。その結果、「10万円程度がちょうどいい」と答えた人が最も多かったのです。
この声を受けて、東証は上場企業に「最低投資金額を10万円程度に引き下げるように検討してください」と要請する方針を2025年4月に発表しました。
背景には「貯蓄から投資へ」の流れ
日本では「貯金」が重視されてきましたが、近年は「貯蓄から投資へ」という流れが強まっています。
その理由は、低金利時代が続き、銀行にお金を預けてもほとんど利子がつかないためです。
一方、投資を通じてお金を増やすことができれば、将来のための資産形成につながります。
しかし最低投資金額が高いと、若い人や投資初心者はなかなか一歩を踏み出せません。
そこで最低投資金額を下げることで、より多くの人が投資に参加しやすくしようという狙いがあるのです。
海外と比べて日本はどうだった?
実は株式投資における最低金額は、日本は海外と比べてかなり高いのが現状です。
- 日本(東証プライム上場企業の中央値):約19万8,000円
- アメリカ(S&P500構成銘柄):約1万8,000円
- フランス:約3,000円
- オーストラリア:約700円
このように、海外では数千円から株が買えるのに対し、日本は10万円以上かかることが多かったのです。
どうやって最低投資金額を下げるの?
企業が「株式分割」という手法をとることで、1株あたりの値段を下げ、最低投資金額を引き下げることができます。
たとえば、1株10,000円の株を2分割すれば1株5,000円になり、100株で50万円だった最低投資金額が25万円に下がります。
東証は、こうした株式分割などの方法で、企業に10万円程度への引き下げを促しています。
最低投資金額引き下げのメリット
① 若い人や初心者が投資を始めやすくなる
10万円程度なら、バイト代やおこづかいをためて投資を始めることも可能です。
これまで「株はお金持ちのもの」と思っていた人も、チャレンジしやすくなります。
② 投資家が増え、株式市場が活性化する
多くの人が投資に参加すれば、市場がにぎやかになり、企業の資金調達もスムーズになります。
③ 株価の変動がゆるやかになる効果も
個人投資家が増えることで、特定の大口投資家による株価の乱高下が起きにくくなると期待されています。
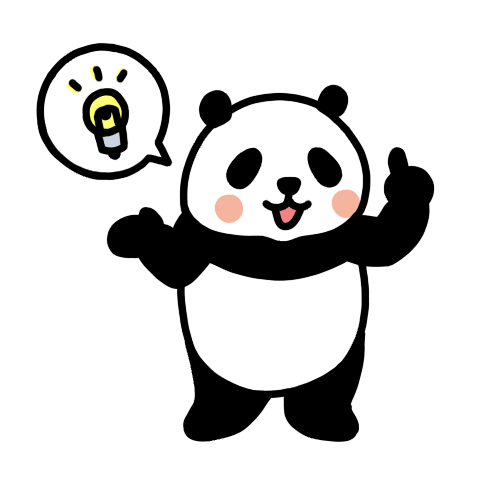
若い人が投資を始めるという意味は資産形成も勿論なのですが、個人的には金融リテラシー(お金の扱い方)を身につけることができるというのが大きなメリットだと思っています。
実際に投資を体験することで、経済ニュースや企業の業績が株価変動を通じて自分事のように捉えられるようになるのが1つ。
所得税、住民税、確定申告、新NISAなど誰もが逃れられない個人の税金に関する知識に興味をもてるようになるのが1つ。
少額でも株価の乱高下を先に体験しておくことで、たとえば年齢を重ねてから初めて投資にチャレンジして退職金などの莫大なお金を突っ込み一気に失うといったリスクを減らせるのが1つ。
Pandaは公認会計士として会計や税務の知識は先にありましたが、実際に投資をしてみると別モノで新発見の連続でした。株価が下がり「自分の財産が減る」という局面になったときの心の動揺も貴重な経験です。
デメリットや課題はある?
① 企業側の事務負担が増える可能性
株主が増えると、株主総会の案内や配当金の支払いなど、事務作業が増えることが考えられます。
ただし、最近は電子化が進み、負担は軽減できるとされています。
② 投資リスクはゼロではない
最低投資金額が下がっても、株価が下がれば損をするリスクはあります。
「少額だから大丈夫」と油断せず、しっかり勉強してから投資を始めることが大切です。
最近話題の「ミニ株」や「単元未満株」とは?
少額投資サービスの概要
2025年現在、証券会社各社が「ミニ株」「単元未満株」と呼ばれる新しい少額投資サービスを次々と拡充しています。聞いたことがある人もいるかもしれません。
これは、1株から株式を買えるサービスで、従来の「100株単位(1単元)」でしか買えなかった日本株を、もっと少ない金額から始められる仕組みです。
たとえば、1株1,000円の会社なら、本来は100株=10万円必要でしたが、ミニ株なら1,000円から投資が可能。
これにより、バイト代やお小遣いでも気軽に株式投資を始めることができるとされています。
主な証券会社のミニ株サービス
- 楽天証券:「かぶミニ®」
2025年4月から取扱銘柄をさらに拡充し、2,182銘柄が1株から購入可能になりました。リアルタイム取引や積立サービス(「かぶツミ」)にも対応し、楽天ポイントでも投資できます。 - SBI証券:「S株」
こちらも1株から日本株を購入でき、数百円から投資が可能です。 - マネックス証券:「日本株積立」
1株単位で定期的に積み立て投資ができる新サービスも始まっています。
ミニ株サービスの注意点
確かにミニ株サービスの登場によって、「数千円~数万円」で株式投資を始めることができる環境が既に整いつつあります。
しかし以下の点には注意が必要です。
- 購入したい銘柄が取扱対象でない可能性がある
- ミニ株は通常の株取引より売買単価が高くなる場合がある(スプレッドや手数料に注意)
- 株主優待や議決権が得られない場合もある(証券会社や銘柄による)
- リアルタイム取引ができる銘柄とできない銘柄がある
まとめ
東証の最低投資金額引き下げ要請と並行して、証券会社の「ミニ株」サービスが拡充され、若者や投資初心者でも、より手軽に株式投資を始められる時代になりました。
「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、より多くの人が株式投資を身近に感じられるようになるでしょう。
ただし投資には必ずリスクがつきものですので、しっかりと知識を身につけてからチャレンジすることが大切です。