MBOは経営者の独断で決まるのか?その舞台裏と本当の決定プロセスを探る

目次
はじめに
MBO(マネジメント・バイアウト)は、会社の経営陣が自社の株式を買い取り、経営権を自分たちで持つようにする仕組みです。上場企業の場合、MBOが実施されると株式は非公開となり、上場廃止になることもあります。
ニュースで「MBO決定!」と聞くと、「社長が決めたのかな?」と思うかもしれません。しかし、MBOは経営者の独断で即決まるような単純なものではありません。ここでは、MBOがどんな流れで決まるのか、できるだけわかりやすく解説します。
MBOのきっかけは経営陣の「こうしたい!」
MBOの始まりは、たしかに経営陣の「会社をもっと自由に経営したい」「長期的な視点で改革したい」といった思いから始まります。
たとえば、株主が多いと、株主の意見をまとめるのに時間がかかり、経営判断が遅れることがあります。また、短期的な利益を重視する株主が多いと、思い切った投資や改革がやりにくい場合もあります。
こうした課題を感じた経営陣が、「MBOをやろう」と考えるのが最初のステップです
MBOの決定は「一声」ではなく、段階を踏む
ただしMBOは、経営者の「やるぞ!」という一声だけで決まるわけではありません。実際には、次のようなステップを踏んで進んでいきます。
1. 会社の価値を調べる
まずは会社の「今の価値」を専門家と一緒に調べます。これを「バリュエーション」と呼び、将来の利益や市場の状況などをもとに、適正な株価を算出します。
2. お金をどう集めるか計画する
経営陣だけで会社を買い取る資金が足りない場合は、銀行や投資ファンドからお金を借りたり、出資してもらったりします。ここで「SPC(特別目的会社)」という、MBOのためだけの会社を作ることも多いです。
3. 社内外の関係者と調整
経営陣だけでなく、親会社や大株主、従業員、取引先など、さまざまな関係者と話し合い、理解や協力を得る必要があります。特に上場企業の場合は、株主の利益を守るための説明や調整が欠かせません。
4. 株式買い付け(TOB)の実施
上場企業の場合、MBOは「TOB(株式公開買付)」という方法で進めます。TOBでは「この価格で株を買います」と公表し、株主から株を買い集めます。
5. 取締役会や株主総会での承認
MBOの実施には、会社の取締役会や、場合によっては株主総会での承認が必要です。ここで反対が多ければ、MBOは実現しません。
6. 第三者委員会の設置
経営陣が自分たちで会社を買うため、価格や条件が公正かどうかをチェックする「第三者委員会」が設置されます。外部の専門家が「この条件は妥当か?」を審査し、株主の利益が守られているか確認します。
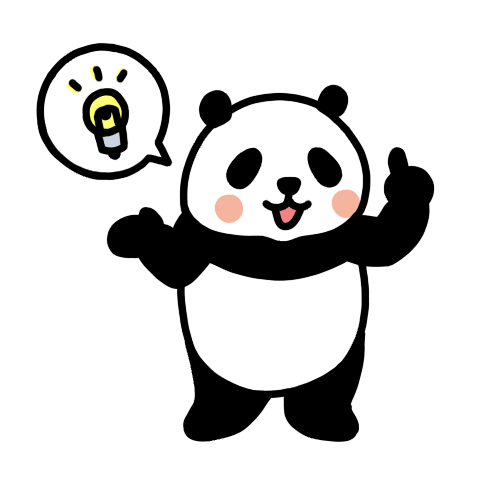
経済社会や従業員とその家族の生活にも影響するとても大きな動きになりますので、社内外の様々な機関との調整が必要になります。
MBOが「決定」する本当の瞬間
すべての準備や調整が整い、取締役会で「MBOを実施する」と正式に決議されたときが、MBOの「決定の瞬間」です。
それまでには、経営陣の強いリーダーシップだけでなく、社内外の合意形成や法的な手続き、資金調達など、たくさんのハードルがあります。
実際の事例:幻冬舎のMBO
たとえば、出版社の幻冬舎は2011年にMBOを実施しました。これは、外部からの敵対的買収を防ぎ、デジタル化への迅速な対応を進めるための決断でした。経営陣の強い意志がきっかけでしたが、実際にはファンドとの交渉や株主への説明、TOBの実施など、多くの段階を踏んで決定されています。
まとめ:MBOは「鶴の一声」ではなく、しっかりしたプロセスで決まる
MBOは、たしかに経営陣の「やりたい!」という思いが出発点ですが、実際には多くの準備や調整、関係者の合意、専門家のチェックを経て、初めて正式に決まります。
ニュースで「MBO決定!」という文言を見たときは、その裏にある複雑なプロセスや関係者の努力を想像してみてください。そこには経営者の意思決定だけでなく、会社全体と多くの専門家が関わる大きなプロジェクトが完了した証でもあるのです。




