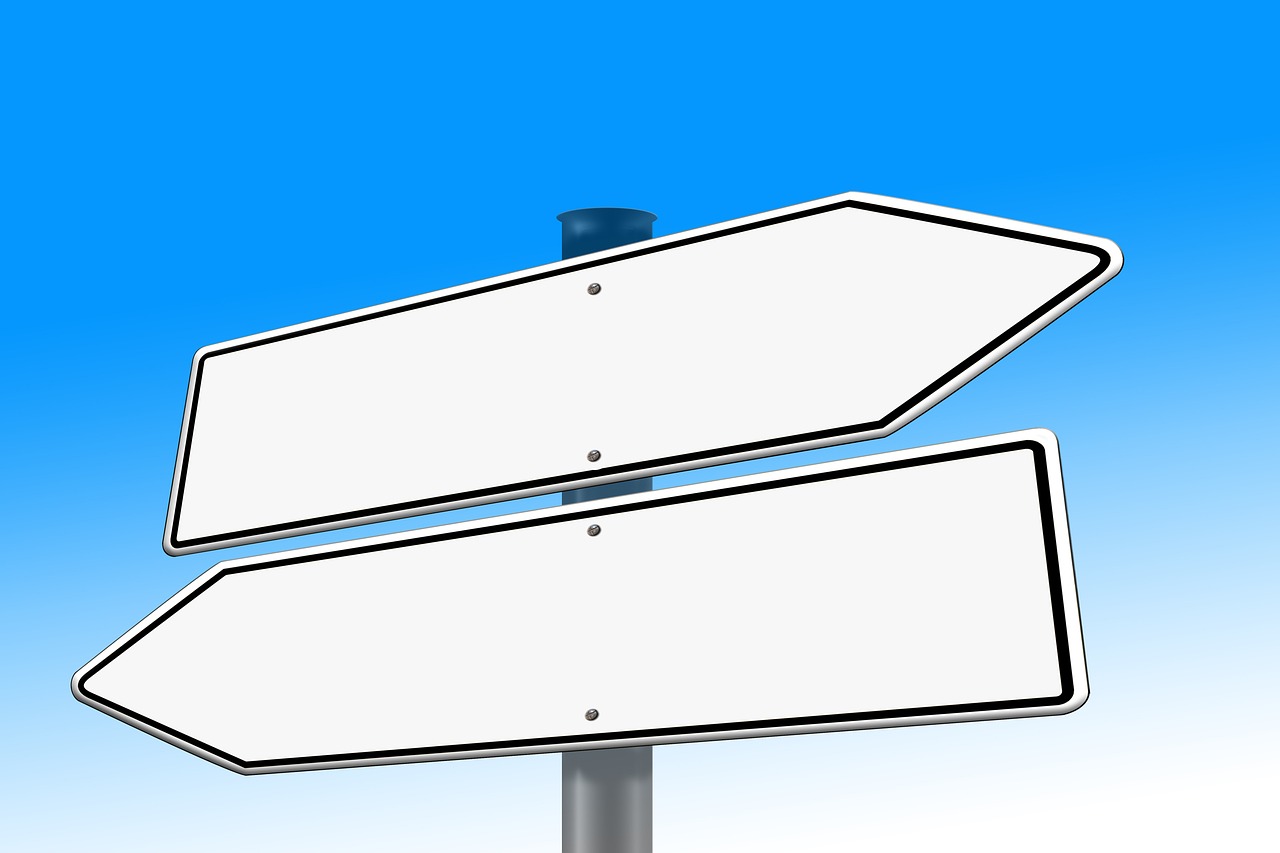東証による改革とは?上場廃止ラッシュや親子上場解消の動向を含めて解説

はじめに
2024年から2025年にかけて、日本の株式市場では「上場廃止」と「親子上場解消」がかつてないペースで進んでいます。
東京証券取引所(東証)の市場改革やガバナンス強化、PBR1倍割れ企業への改善要請などを背景に、上場維持のハードルが高まり、企業は“上場し続ける意味”を改めて問われています。
また、親会社と子会社がともに上場する「親子上場」も、利益相反や経営効率の観点から世界的に問題視されてきました。
本記事では、上場廃止や親子上場解消がなぜ加速しているのか、最新の事例や投資家への影響も交え、わかりやすく解説します。
上場廃止ラッシュの背景――東証改革と新たな基準
2025年3月、東証はプライム・スタンダード市場の「経過措置期間」を終了し、新たな上場維持基準を本格適用しました。
この結果、流通株式時価総額やガバナンス体制、資本効率などの条件を満たせない企業は、上場廃止や市場変更(いわゆる“都落ち”)を迫られています。
なぜ今、これほど上場廃止が増えているのか?
最大の要因は、東証改革により「上場企業の“量”より“質”」が重視される時代に突入したことです。
ガバナンスや資本効率、女性役員登用などグローバル基準の厳しいチェックが入り、基準を満たせない企業は容赦なく市場から退出を迫られるようになりました。
東証が求める厳しい基準とは?
東証は、企業経営がより透明で効率的、かつ多様性を重視したものへと進化することを求めています。
1. ガバナンス(企業統治)の強化
東証はプライム市場を中心に、”世界の機関投資家が安心して投資できる「高いガバナンス水準」”を企業に求めています。
具体的には、
- 独立社外取締役を3分の1以上選任(場合によっては過半数も検討)
- 取締役会の機能強化(経営の監督・監視、CEOの選解任や報酬決定など)
- 指名委員会・報酬委員会の設置と機能充実
- スキルマトリックスの開示(取締役の専門性や多様なスキルを一覧で開示)
これにより、経営陣の暴走や利益相反を防ぎ、企業価値の持続的な向上を目指します。
2. 資本効率の重視
グローバル投資家は、企業が「どれだけ効率よく資本を使って利益を生み出しているか」を重視します。
東証はこれを受けて、
- ROE(自己資本利益率)やROIC(投下資本利益率)など資本収益性の指標を重視
- 資本コスト(WACCや株主資本コスト)を意識した経営計画の策定・開示
- PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業への改善要請
などを求めています。
企業は、単なる売上や利益の大きさだけでなく、「投資家から預かった資本をどれだけ有効活用しているか」を説明し、改善策を示すことが必須となっています。
3. 女性役員登用など多様性の確保
取締役や管理職への女性・外国人・中途採用者の登用も、グローバル基準の重要な要素です。
東証のコーポレートガバナンス・コードでは、
- 中核人材の多様性確保のため、女性や外国人の登用状況や目標を開示すること
- 多様なバックグラウンドを持つ人材が意思決定に関与することで、企業の競争力やイノベーションが高まる
とされています。
これにより、日本企業も世界標準に合わせ、ダイバーシティ経営を強化する流れが加速しています。
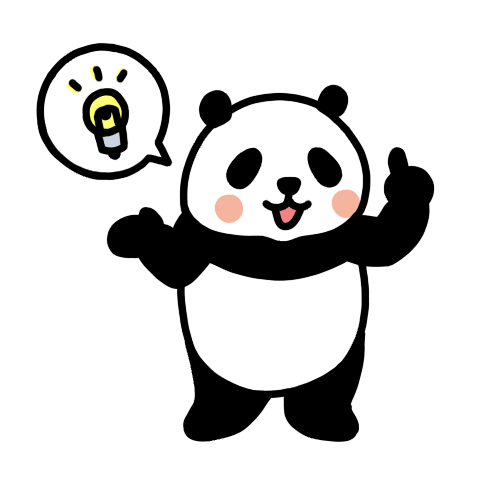
一言でいえば、世界の投資家が納得できる透明性・効率性・多様性の高い企業経営を実現することを意味しています。
冒頭で述べた”経過措置期間の終了”についてはこちらも参照ください。

上場廃止の主なパターン――強制退場と自主的な非公開化
上場廃止には大きく2つのパターンがあります。
① 基準未達による「強制退場」
- 流通株式時価総額やガバナンス基準を満たせない企業は、東証から「上場廃止予備軍」として警告を受け、改善できなければ強制的に市場から退場となります。
- 2025年3月の経過措置終了で、こうした企業の“淘汰”が一気に進んでいます。
② 経営判断による「自主的な非公開化」
- 近年はMBO(経営陣による自社買収)や親会社によるTOB(株式公開買付)を通じ、企業自ら上場廃止を選択するケースが急増しています。
- 背景には「上場コストの増加」「情報開示や株主対応の負担」「資本効率重視の流れ」などがあります。
親子上場解消トレンドの加速
「親子上場」とは、親会社と子会社がともに上場している状態を指します。
かつては資金調達や知名度向上のメリットが強調されていましたが、近年は利益相反やガバナンスの問題が指摘され、世界的に見直しが進んでいます。
親子上場解消の背景
- 利益相反の懸念:親会社が子会社の経営に強い影響力を持つことで、少数株主の利益が損なわれるリスクがある。
- ガバナンス強化の流れ:東証改革で経営の透明性や資本効率が重視され、親子上場の「解消」が推奨されるようになった。
- 経営効率の向上:グループ全体での意思決定の迅速化や経営資源の最適配分が狙い。
実際の動き
- 2024年はイオンがイオンモールとイオンディライトの2社を完全子会社化すると発表し、他の大手企業にも波及しています。
- 富士通が富士通ゼネラル、日本製鉄が山陽特殊製鋼の完全子会社化を進めるなど、2025年も親子上場解消の動きは加速しています。
- 2023年度の親子上場企業数は190社と、ピークの2006年度から半減。17年連続で減少しています。
親子上場解消の主な方法と事例
親子上場を解消する方法には主に2つあります。
①親会社による子会社のTOB・完全子会社化
- 親会社が子会社の株式をTOB(株式公開買付)で取得し、100%子会社化した上で上場廃止とする
- 例:ローソン(2024年7月上場廃止、三菱商事とKDDIの共同経営体制へ)、イオンモール・イオンディライト(2025年完全子会社化へ)
②親会社が子会社株式を売却し、資本関係を解消
- 親会社が持ち株を第三者に売却し、親子関係を解消する
- 例:日立製作所は一部子会社でこの方法を選択
③一部株式売却による資本関係の見直し
- トヨタ自動車がデンソー株を一部売却し、資本効率の改善とグループ再編を進めている
まとめ
上場廃止や親子上場解消は、東証改革やグローバルなガバナンス強化の流れを背景に、今後も加速していくと見られます。
企業にとっては経営効率やガバナンス強化のチャンスであり、投資家にとってはプレミアム獲得や出口戦略を考える重要な局面です。
これからも日本の株式市場では、非公開化やグループ再編が大きなテーマとなるでしょう。
投資家・経営者ともに、最新動向をしっかりウォッチし、変化の波をチャンスに変えていくことが求められます。