東証の上場維持基準“経過措置”終了とは?2026年3月末が運命の分かれ道
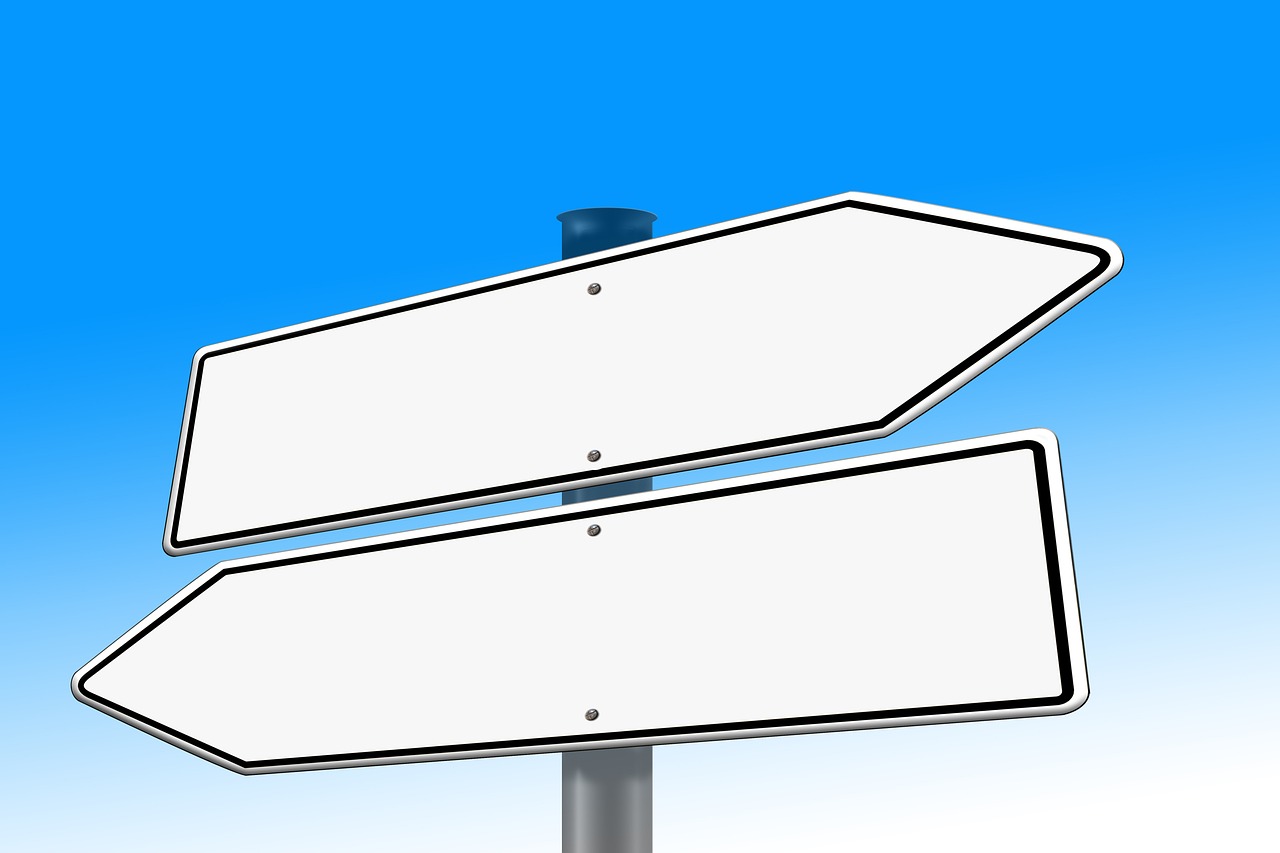
目次
はじめに
2025年3月、東京証券取引所(東証)が上場企業に適用してきた「上場維持基準の経過措置」がついに終了しました。これにより、基準を満たしていない企業は1年間の改善期間に入り、2026年3月末までに基準をクリアできなければ、原則として同年10月1日に上場廃止となります。
この記事では、この「経過措置」終了の意味・背景・今後の流れをやさしく解説します。
上場維持基準とは?
まず「上場維持基準」とは、東証に上場し続けるために企業が守らなければならないルールのことです。例えば、以下のような基準があります。
- 株主数(例:プライム市場なら800人以上)
- 流通株式数や時価総額(例:プライム市場なら100億円以上)
- 流通株式比率(例:プライム市場なら35%以上)
- 売買代金や売買高 など
これらの基準を満たしていないと、東証の市場に上場し続けることができません。
経過措置って何?
2022年4月、東証は市場を「プライム」「スタンダード」「グロース」の3つに再編し、それぞれで上場維持基準を厳しくしました。しかし再編時点で新しい基準を満たしていない企業も多かったため、すぐに上場廃止の扱いにはせず2025年3月までの期間を「経過措置」として一定期間は緩い基準で上場を認めてきました。
この経過措置は、企業に「新しい基準に合わせて経営を改善する時間」を与えるためのものです。
2025年3月、ついにこの経過措置が終了しました。これにより、今後は「本来の上場維持基準」がすべての企業に適用されます。
企業のスケジュール(3月決算の場合)
経過措置が終了し、”改善期間”に突入
“改善期間”が終了。この時点で基準を満たしていないと、”監理・整理銘柄への指定”へ移行される
原則として”上場廃止”
つまり、3月期決算の企業は「あと1年以内で基準を満たさないと上場廃止」という状況になったのです。
どんな企業が対象?
経過措置終了時点で基準を満たしていない企業は、プライム市場69社、スタンダード市場143社、グロース市場47社など、合計で230社以上にのぼります(2024年末時点)。
企業はどうすればいいの?
基準を満たしていない企業は、2026年3月末までに以下のような対応を迫られます。
- 株主数を増やす
- 流通株式数や時価総額を増やす(新株発行や株主還元など)
- 株式の流動性を高める(株式分割やPR活動など)
- 売買高を増やす(投資家へのアピール強化など)
もし基準を満たせない場合は、上場廃止のリスクが現実となります。
東証としては一定の基準をクリアした企業だけが残れば「選ばれた企業の市場」として日本の株式市場の質を高められ、投資家や世界からの信頼を得ることができると考えています。
上場廃止になるとどうなる?
上場廃止になると、その企業の株は東証で売買できなくなります。投資家は株を現金化しづらくなり、企業も資金調達の面で不利になります。また、社会的な信用も低下するため、企業にとっては大きな痛手です。別記事でメリットもあることは紹介していますがこのようにデメリットもあります。
企業の選択肢は?
基準を満たせない企業は、以下のような選択肢を検討しています。
- 基準の達成を目指す:経営改善や株主対策を急ぐ
- 市場区分の変更:プライムからスタンダードなど、基準がより緩い市場へ移行(ただし、一定期間の移行猶予あり)
- 上場廃止(非公開化):MBO(経営陣による自社買収)や他社による買収などで上場をやめる
- 地方取引所への移行:東証以外の証券取引所への上場を検討する企業も
まとめ
- 東証は2025年3月で「上場維持基準の経過措置」を終了
- 基準未達の企業は2026年3月末までに改善しなければ、原則10月1日に上場廃止
- 対象は230社以上。企業は基準達成や市場区分変更などの選択を迫られる
- 市場の「質」を高めることで、日本の株式市場の信頼性アップを目指している
今回の経過措置終了は、日本の株式市場にとって大きな転換点です。これから1年、基準未達の企業は「生き残り」をかけてさまざまな改革に取り組むことになります。投資家にとっては、どの企業が基準をクリアできるのか、どんな経営戦略を打ち出すのかが注目ポイントです。
ニュースや新聞で「上場廃止」や「市場再編」という言葉を見かけたら、「企業の選別が進んでいる」「日本の株式市場がレベルアップしようとしている」とイメージしてみてください。





