MBOが急増する背景とは?東証改革・PBR1倍割れ・事業承継問題をわかりやすく解説

目次
はじめに
最近、「MBO(経営陣による自社買収)」という言葉をニュースや株式投資の話題でよく見かけませんか?大正製薬やベネッセなどの有名企業がMBOを発表し、株価が急騰したことも記憶に新しいでしょう。
2023年度のMBOによる株式取得額は過去最高の1.4兆円を記録しました。では、なぜ今、MBOが日本で急増しているのでしょうか?
実はその背景には、東証(東京証券取引所)の市場改革や、PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業への改善要請、さらには中小企業を中心とした事業承継問題など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
この記事では、MBOが増えている理由を、できるだけわかりやすく解説します。
MBOが増えている4つの理由
1. 東証の市場改革と資本効率の改善要請
2022年、東証は市場区分を再編し、上場企業に対してより厳しい基準やガバナンス(企業統治)を求めるようになりました。
さらに2023年以降は、「資本コストや株価を意識した経営」を強く要請し、特にPBRが1倍を下回る企業に対しては、改善策の開示を義務づけています。
これにより、企業は
- 上場維持のためのコストや情報開示の手間が増える
- 株価や資本効率を意識した経営改革を迫られる
- 割安な株価が続くと、上場のメリットが薄れる
といった状況に置かれるようになりました。
その結果、「いっそ上場をやめて非公開企業になり、自由に経営したい」と考える経営陣が増え、MBOの動きが加速しています。
2. PBR1倍割れ企業への市場からの圧力
PBR(株価純資産倍率)が1倍を下回る企業は、「会社の資産価値よりも株価が安い=市場から成長期待が低い」と見なされます。
東証はこうした企業に対し、改善策を公表するよう強く求めています。
※PBR=株価/1株あたり純資産
例えば、
株価が1,000円で1株あたり純資産が500円なら・・・PBRは2倍
株価が1,000円で1株あたり純資産が1,500円なら・・・PBRは0.67倍
しかし、どんなに経営努力をしても株価がなかなか上がらない場合、経営陣は「上場している意味が薄い」と感じることも。
そのため、MBOや親会社による完全子会社化(TOB)を選ぶ企業が増えています。
また、MBOの際のTOB価格がPBR1倍未満で提示されることも多く、少数株主の保護や価格の妥当性が社会的な課題にもなっています。
3. アクティビスト(物言う株主)の台頭
近年、アクティビストと呼ばれる「物言う株主」が日本企業に対して積極的に意見を述べるようになりました。
彼らは、配当増額や自社株買い、事業再編、時にはMBOや上場廃止を要求します。
経営陣からすると、こうした外部からの短期的な要求に振り回されるより、MBOで非公開化し、長期的な成長戦略に集中したいという動機が強まっています。
4. 事業承継問題と中小企業のMBO
中小企業では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっています。
親族や社外への事業承継が難しい場合、経営陣や従業員が会社を引き継ぐMBOが有力な選択肢となっています。
MBOなら、会社の文化や経営方針を守りながら、スムーズな事業承継が可能です。
こうした理由から、中小企業でもMBOが増加しています。
MBO増加がもたらす変化
MBOによって企業が非公開化すると、経営の自由度が高まり、中長期的な成長戦略に集中しやすくなります。
一方で、株主が市場で株を売れなくなる、資金調達の選択肢が減るなどのデメリットもあります。
それでも、東証や市場からのプレッシャー、事業承継問題などを背景に、今後もMBOや上場廃止を選ぶ企業は増えていくと見られています。
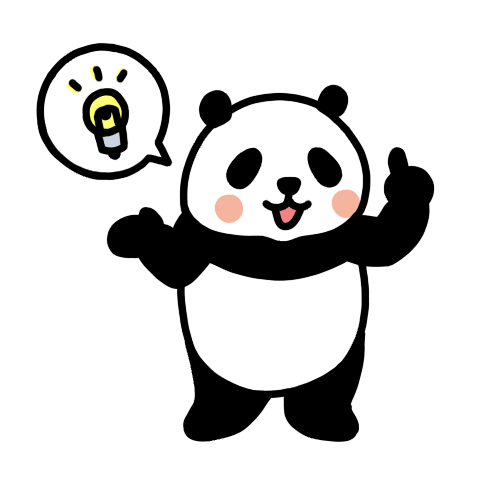
上場廃止したといっても業績悪化による退場のようなネガティブな理由とは限らず、それ相応の理由がありそうですね
まとめ
MBOが急増している背景には
- 東証の市場改革と資本効率改善要請
- PBR1倍割れ企業への市場からの圧力
- アクティビスト(物言う株主)の増加
- 事業承継問題の深刻化
など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
今後もMBOや上場廃止の動きは続くと予想されます。投資家や経営者は、こうした市場環境の変化をしっかりと理解し、適切な判断をしていくことが大切です。


