MBO候補を探せ!注目すべき特徴やスクリーニング方法について

目次
はじめに
2024年から2025年にかけて、日本の株式市場ではMBO(経営陣による自社買収)が大きな注目を集めています。大正製薬HDやベネッセホールディングスなど、上場企業による大型MBOが相次ぎ、投資家の間では「次はどこがMBOを実施するのか?」という予想合戦が活発化しています。この記事では、MBOが起こりやすい企業の特徴や、データをもとにした注目企業のスクリーニング方法について詳しく解説します。
なぜ今、MBOが増えているのか
2024年のM&A市場は、TOB(市場外での株式買い集め)やMBOの案件が非常に目立ちました。背景には、東証による市場改革や株価是正要請、上場維持コストの増加、企業ガバナンス強化の流れなど、さまざまな要因が複合的に絡み合っています。特に、東証スタンダードやプライム市場の上場維持基準の見直し、PBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業への圧力、事業承継問題の深刻化などが、企業経営に大きな影響を与えています。
2025年以降も業界再編や企業統合が加速する見通しといわれています。上場企業による”上場廃止”の動きだけでなく、中堅・中小企業においても特に事業承継問題が深刻化している場合など、MBOやTOBを活用した再編が今後も増えると予想されています。
MBO候補企業の特徴
MBOが起こりやすい企業には、いくつかの共通した特徴があります。これらの条件をもとに、候補企業をスクリーニングすることが可能です。
ちなみにスクリーニングとは「たくさんある中から条件に合うものをふるいにかける作業」のことをいいます。株式投資においては具体的に、証券会社のスクリーニングツールやデータベースを使い条件に合う企業をリストアップします。
- PBR1倍割れ・株価低迷
PBRが1倍を下回っている企業は、株式が純資産価値よりも割安に放置されていると評価されます。こうした企業は、経営陣が「市場評価が低すぎる」と判断し、MBOによる非公開化を選択するケースがあります。 - オーナー経営・大株主の存在
創業家や経営陣が大株主となっている企業は、意思決定がしやすく、MBOの実施ハードルが低い傾向にあります。特に事業承継問題を抱える企業では、MBOが有力な選択肢となります。 - 財務体質が健全
MBOには多額の資金が必要なため、自己資本比率が高く、借入余力のある企業が候補となりやすいです。 - 東証スタンダード・プライムの時価総額上位
東証スタンダードやプライム市場の上場基準を満たしつつも、流動性や市場評価の問題から非公開化を選ぶ企業が増えています。 - 親子上場・持株会社構造
親会社と子会社の時価総額や株価評価に「ねじれ」が生じている場合、MBOや親会社による完全子会社化が起こりやすいです。
2024年にMBOを実施した大正製薬HDは、東証スタンダード上場で時価総額も高い水準にありました。こうした企業は、今後もMBO候補として注目されます。
2024~2025年のMBO実施事例
【大正製薬ホールディングス】
2024年11月、過去最大規模となる約7100億円でMBOを実施。TOB価格は終値に対して大幅なプレミアムが付与されました。背景には、主力事業の不振や経営の自由度確保がありましたといわれます。
【ベネッセホールディングス】
2024年11月、約2700億円でMBOを実施。TOB価格は終値よりも高く設定され、株主にとっても注目案件となりました。
【アイロムグループ】
2025年3月、代表取締役社長が筆頭株主としてMBOを実施。今後も中堅企業で同様の動きが増えると見られています。
【トプコン】
2025年3月、経営陣とファンドが連携しMBOを実施。成長戦略の加速と企業価値向上が狙いとされました。
MBO候補を探るためのスクリーニング方法の一例
- 財務データのチェック
PBR1倍割れ、自己資本比率40%以上、連続増益・安定配当。これらの条件を満たす企業は、MBOの資金調達が容易で、株主からの反発も受けにくい傾向があります。 - 株主構成の分析
創業家・経営陣の持株比率が高い、特定株主に集中している。このように株主構成が安定している企業は、意思決定が迅速でMBOの実施が現実的です。また経営者の事業承継や相続対策のためにMBOが用いられることがあります。 - 市場・業界動向の把握
業界再編の動きが活発な分野(製薬、鉄鋼、化学、金融など)は再編が進む業界として特に注目です。世界と戦うために日本の業界1位と2位がタッグを組むという動きもあります。
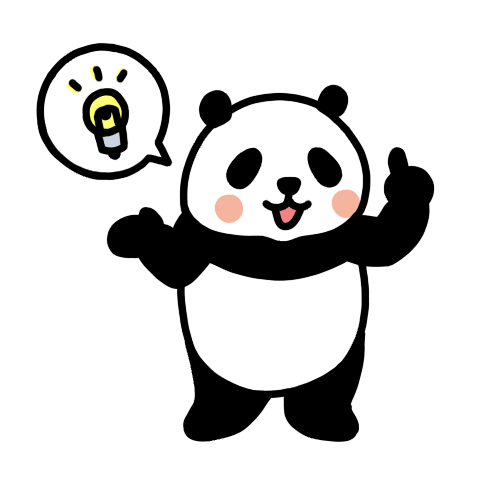
詳細についてはまた別記事でご紹介しますね
投資家が注意すべきポイント
MBO候補を狙った投資は、短期間で大きなリターンを得られる可能性がありますが、リスクも存在します。
- TOB価格が期待より低い場合、株価が下落するリスク
- MBOが実施されない場合、株価が低迷するリスク
- 経営陣と株主の利害対立によるTOB不成立のリスク
また2025年からは東証の関連施策も強化され、MBOや親子上場に関する規程の見直しや、株式価値算定の開示充実が進められています。こうした制度変更も投資判断の材料に加える必要があります。
まとめ
MBOは今後も日本企業の経営戦略や投資家の注目テーマとなり続けるでしょう。PBR1倍割れやオーナー企業、財務体質が健全な企業、親子上場のねじれ銘柄など、データをもとに候補企業をスクリーニングすることで、次のMBOを先回りする投資戦略が可能です。ただし、リスクも十分に理解し、冷静な分析と分散投資を心がけることが大切です。
2025年もMBO関連のニュースや市場動向に注目し、データを活用した先見的な投資判断を目指しましょう。

